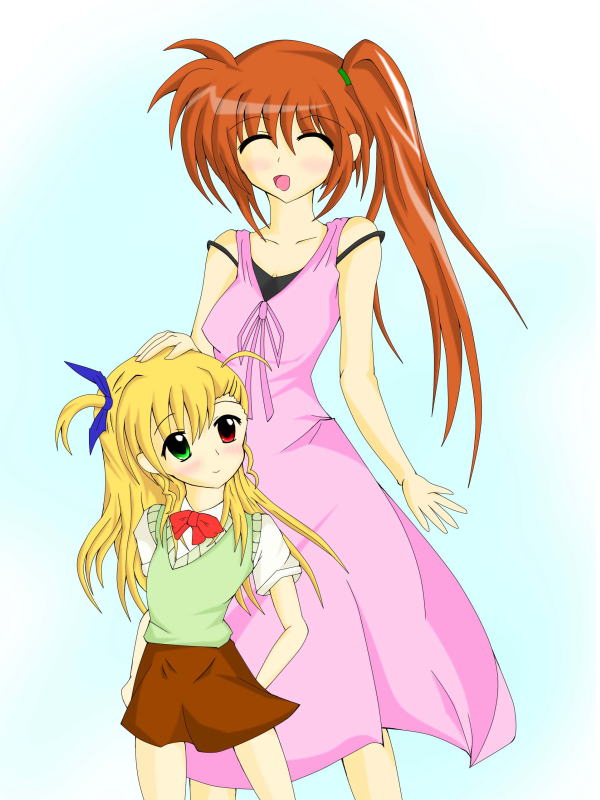
――戦いが終わった。
苦しくて、つらい、悲しい戦いだったけれど、全て終わりを告げた。
私の所属していた機動六課も解散することになった。
機動六課はもともと試験運用だったのだ。役目が終われば解散することも当たり前だ。
これでみんなともお別れだ。
みんなそれぞれの道を歩んでいく。
だけど、私は別れを悲しんだりはしない。
機動六課は皆にとっても私にとっても、もっと先に羽ばたくための通過点だったのだ。
たとえ一年という短い間だとしても、そこで繋げた絆は消えることなんてない。
そして、この戦いは私にとても大切なものを残していった。
それは、私をママと呼んでくれる大切な子。
――ヴィヴィオ。
想いと想いをぶつけ合って、本当の絆を手に入れることが出来た。
これから護っていくと決めた女の子。
本当に……本当に大切な存在。
私はぼんやりとヴィヴィオのことを想う。
「――ねぇ〜、なのはママ〜」
「……あっ、ごめんね、ヴィヴィオ。少し考え事をしてたんだよ」
ヴィヴィオの呼ぶ声に気付き、ハッとして慌てて返事をする。
どうやら、ぼんやりし過ぎていたようだ。
「なのはママにお願い事があるの……」
「……お願い事? なぁに、ヴィヴィオ、言ってごらん」
ヴィヴィオがお願いを言うなんて珍しい。
甘えてくることは多いけれど、こんなふうにお願いをされるのは初めてのことだ。
目をウルウルさせてこちらを見るヴィヴィオは、とっても可愛くて抱きしめたくなったけれど、今は我慢した。
「……学校に……いってみたいの……」
「……えっ!」
その言葉にはびっくりした。
だけど、ヴィヴィオがそう思うのも仕方がないかもしれない。
今まで普通の生活を遅れなかったヴィヴィオ。ヴィヴィオが普通の生活に憧れるのは当たり前だ。
だから私はその願いを叶えてあげたいと思う。
「……うん、分かったよ。ママがそのお願いを叶えてあげる」
「わぁ〜 ありがとう、なのはママ!」
ヴィヴィオの顔が嬉しさでいっぱいになる。
その笑顔を見れただけで、私は幸せだ。
そして嬉しさのあまり抱きついてきたヴィヴィオを優しく抱き止めてあげる。
――私はこの笑顔を見続けたいと想った。
「うーん、困った……」
「どうしたの、なのは?」
私の独り言はどうやらフェイトちゃんに聞かれていたようだ。
一人ではこの問題は解決できそうもなかったので、フェイトちゃんに意見を聞いてみた方がいいのかもしれない。
「……ヴィヴィオがね、この間“学校に行きたい”っていったんだけどね……」
「ヴィヴィオが?」
うん、と軽く頷く。
どうもフェイトちゃんも驚いているようだ。
「……でね、私としてはヴィヴィオにはちゃんと学校に行って欲しいんだけど……」
「うん、そうしたほうがいいと思うよ」
「だけど……」
「だけど?」
この先のことはちょっと恥ずかしいので言いにくい。
フェイトちゃんがこっちを見ている。
「…………入学届けのね……保護者の父親の欄、どうしようかなぁ……って」
「……はぁ」
――呆れられたような目でフェイトちゃんに見られました。
「……なのは、そんなの決まってるよ」
「……えっ?」
そんなことを言われても、このことは結構大変な問題だと思うんだけどなぁ。
そんなに簡単なことなのかな?
「ユーノの名前を書けばいいよ」
「ええええぇぇぇーー!!」
予想外の言葉に頭の中がグルグル回った。
だってユーノ君は……確かに恋人だけど、さすがにこれはユーノ君にも迷惑というか……
確かにそうなって欲しいけど、それは私の願望でもあるけれど、やはりそれは……
「ふぇ、フェイトちゃん!? た、確かにユーノ君は私の恋人さんだけど、そうなってくれたら嬉しいし、いいことだけど、さすがにそれはユーノ君に迷惑だと思うし、だけど……」
「なのは……何言ってるか、分からないよ」
フェイトちゃんにコツンと頭を叩かれた。
それから数分、頭がフワフワしていたけれど、何とか落ち着くことが出来きた。
「……大丈夫だよ、なのは。ユーノならきっと父親を引き受けてくれるよ」
「…………うん……聞いてみる」
携帯をポケットから取り出す。
緊張とドキドキでボタンを押す手が震えているのが分かる。
「……なのは、そんなに緊張しなくても……」
「……だってぇ〜」
フェイトちゃんが私の顔を見てクスリと笑った。
どうやらものすごく情けない顔をしていたようだ。
「女は度胸だよ」
「女は度胸……」
やっとのことでボタンを押し終える。
私が心の準備をする間もなく、コール音が鳴り響く。
この時間帯は確かユーノ君は休憩のはずだ。必ず電話を取るだろう。
――コール音が途切れるまでの時間が、とても長く感じられた。
『――もしもし、なのは?』
「……うん、なのはだよ」
緊張のせいで少し上ずった声がしてしまった。
胸のドキドキが止まらない。
『どうかしたの? なんだか声の感じがいつもと違うけど……』
「ううん、なんでもないの! ……でね、ユーノ君にお願いがあるんだけど……」
『お願い?』
「……うん」
さらに胸の高鳴りが高まる。
このお願いが叶うと、もっとユーノ君との関係は縮まるのだ。
それは嬉しいことだけど、どうしても緊張してしまう。
――恋する女の子は複雑なのだ。
「……あのね、ヴィヴィオがね……学校に行きたいって言ったの」
『……うん、それで?』
「ユーノ君にねヴィヴィオの保護者になってほしいの…………お父さんに……」
『………………』
ついに言ってしまった。
恥ずかしさで死にそうだ。顔が真っ赤になる。
ユーノ君の返事はまだ来ない。――無言だ。
やっぱりこんなことは迷惑だったのだろうかと、不安が頭の中を駆け巡る。
無言の時間が数分にも数時間にも感じられた。
『――なのは……それは、プロポーズって受け取っていいのかな?』
予想をはるかに超えた言葉だったので私は一瞬気をどこかにやってしまった。
プロポーズ――それは、二人の永遠の愛を誓い合う言葉。
そんなつもりはなかったのに。そういう訳ではなかったのに。
「……えっ、えええ……えええぇぇぇぇ〜〜」
驚きでユーノ君が何を言っているのか分からない。
あわてて言葉を返す。
「……ち、ちがうの!」
「……違うの?」
その言葉に赤かった顔はさらに真っ赤に染まった。
確かにユーノ君と結婚はしたいけど、その言葉を伝えるのはもっと先のことだ。
それに……もっと雰囲気がある場所がよかったのに。
もう後の祭りだ。
私が何も言えずにいると、ユーノ君が話しかけてきた。
「……分かってるよ、なのは。そんなつもりは無いってことは……だから、このことは次に逢ったときにしようか」
「…………うん」
次に逢うとき。
それはそんなに遠くない未来だ。
そのときまでには、私も覚悟を決めるのだ。……一歩先に進む覚悟を。
「……で、ヴィヴィオのことだね。よろこんで、ヴィヴィオの父親役をやらせてもらうよ」
「……ほんとに! 迷惑じゃない?」
「迷惑なんてことないよ……時間が空いたらそっちに行くよ。久しぶりにヴィヴィオにも会いたいからね」
「わかったよ、楽しみに待ってるね」
そして携帯電話を切る。
久しぶりにユーノ君に会える……それだけで嬉しさが込上げてくる。
――私は幸せな気分にひたりながら数日を過ごした。
電話から数日後。
僕はなのはとヴィヴィオに会いに来ていた。
二人に会うのは久しぶりだ。――本当に楽しみだ。
「――ユーノ君っ!」
「ユーノパパ!」
後から誰かが抱きついてくる。
僕は振り返り、その子を優しく抱き上げる。
「――久しぶり、ヴィヴィオ。それになのはも」
ヴィヴィオが僕に頬をすり寄せてくる。
そんな仕草、ひとつひとつがとても可愛らしく感じられる。
「ユーノ君、ヴィヴィオの父親のこと本当にありがとうね」
「電話でも言ったけど、全然気にしてないよ」
ヴィヴィオを地面に下ろして、なのはの方を向く。
「……で、電話のときの話だけど……」
「………………うっ……」
なのはのプロポーズ未遂のことを話し始めたら、なのはは目の前で真っ赤になってしまった。
「……いいよ、なのは。ゆっくりと……ゆっくりと前に進もう」
「…………うん」
「焦る必要はないんだ。二人で、ヴィヴィオを見守っていこう」
僕は微笑みながら、なのはを見つめる。
なのはも微笑みながら、僕を見つめる。
このまま抱きしめて、キスでもしたかったけど、ヴィヴィオの前だと思いグッと我慢する。
「……なのはママ、ユーノパパ、何してるの?」
話に置いてけぼりにされてつまらなくなったのか、少し拗ねたような声でヴィヴィオが話しかけてくる。
そこで僕はヴィヴィオを見て、改めて気付いたことがあった。
「……そういえばヴィヴィオ。その服……」
「がっこうのせいふくだよ〜」
「やっと気付いた。ユーノ君、気付くの遅いよ」
学校の制服なんだ、となのはが説明をしてくれた。
その制服はヴィヴィオにとても似合っていた。
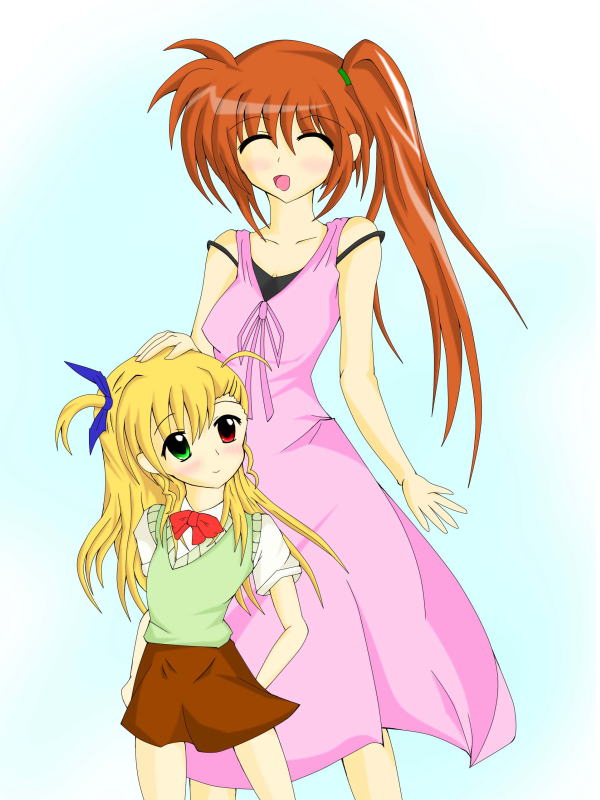
「よく似合ってるよ」
「ありがとうっ、ユーノパパ」
ヴィヴィオがまた抱きついてくる。
それをまた抱き止めて、ヴィヴィオの鼓動を感じる。
ヴィヴィオを抱きしめながら、なのはと顔を見合す。
そして、二人で微笑みあう。
――その瞬間に何事にも変えがたい幸せを感じられる。
この幸せがいつまでも続けばいいと思う。
永遠など無い。だけど、永遠を夢見る。
――僕は、二人と歩き続ける。
END
あとがき
タイトルが『学校へ行こう!』のはずなのに、学校へ行ってませんwwもうちょっとマジメにタイトルを考えればよかった……
これは、甘々SSなのでしょうか?それともほのぼのSSなのでしょうか?――自分ではもう判断できません。
もうちょっと、絵をちゃんと描きたかったな……そこが一番の反省点です。
SSのページに戻る トップページに戻る