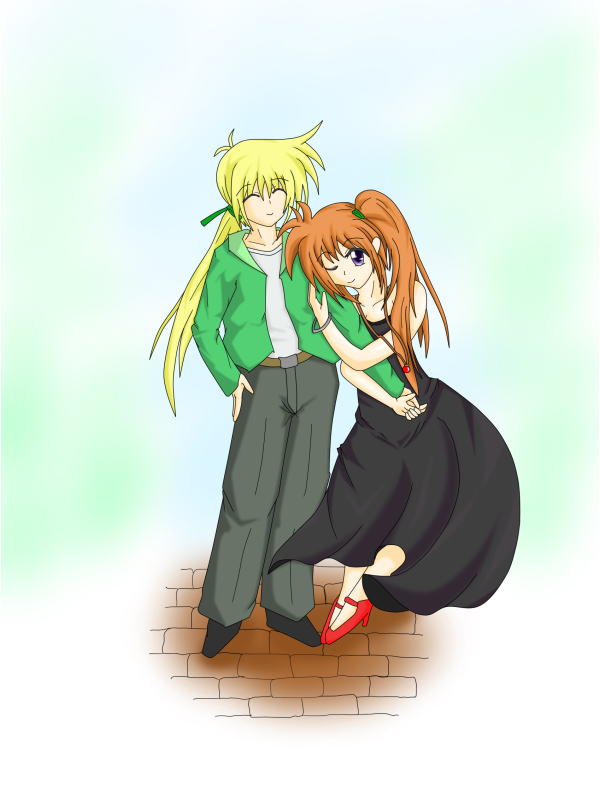
「――ちょっと早く来すぎたかなぁ?」
ミッドチルダの中央に位置する公園に私、高町なのはは来ていた。
どうも早く来すぎてしまったようだ。まだ彼は来ていないようだった。
今日は待ちに待った、ユーノ君とのデートだ。
珍しくユーノ君からのお誘いのメールが届いた。
いつもなら私からデートの約束をするのだ。
彼は仕事熱心な人だから、時間が空いてもデートよりも仕事を入れてしまうことが多い。
まぁ、私よりも仕事を優先してしまうユーノ君には、ちょっとだけ『むっ』っと思ってしまう。
だけど、ユーノ君の仕事の大切さも、責任感の強さも解っているから、そんな彼を許してしまう。
結局、どう考えたって私はユーノ君のことが大好きなのだ。
……で、話を戻すとユーノ君からデートのお誘いがあるのは珍しいことなのだ。
昨日の夜は、ドキドキやらワクワクで中々寝付けなかった。
明日はユーノ君とどんなことを話せるのだろう?
明日はどのくらいユーノ君と居られるのだろうか?
そんなことばかり考えながら布団の中でもんもんとしていた。
待ち合わせの約束の時間まであと三十分くらい。
ポケットから手鏡を出して、身だしなみの最終確認。
服が変になっていないか? 髪が変になっていないか?
ユーノ君に会うのだ。幻滅されるのは嫌だし、最高の自分を見て欲しいと思う。
今日の服装は黒いワンピースだ。
肩が広く出ている、いつもの服装よりもちょっぴり大胆なものだ。
ユーノ君はどんなことを言ってくれるのか想像するだけでドキドキする。
私は公園の噴水の前のベンチでユーノ君を待ち続ける。
「――おまたせっ、なのは」
「……久しぶり、ユーノ君っ」
あれから十五分。待ち望んだ時がやってきた。
久しぶりのユーノ君の顔。
「私すっごく、楽しみにしてたんだよ」
「……そうなの?」
長いこと会っていなかったのに、ユーノ君の返事はそっけなく感じた。
私なんてユーノ君と会うのが楽しみで夜も眠れなかったというのに。
――なんか不公平だ。
「むぅ〜 なんかユーノ君そっけない。彼女との久しぶりのデートだっていうのに……」
私は頬を膨らませて、そんな愚痴をこぼしながらも、ユーノ君の傍まで歩いて、腕を絡める。
我ながら言っていることと、やっていることが違うなと思う。
だけど、腕を絡めるというユーノ君の温もりをいっぱい感じられるこの体勢は大好きだ。
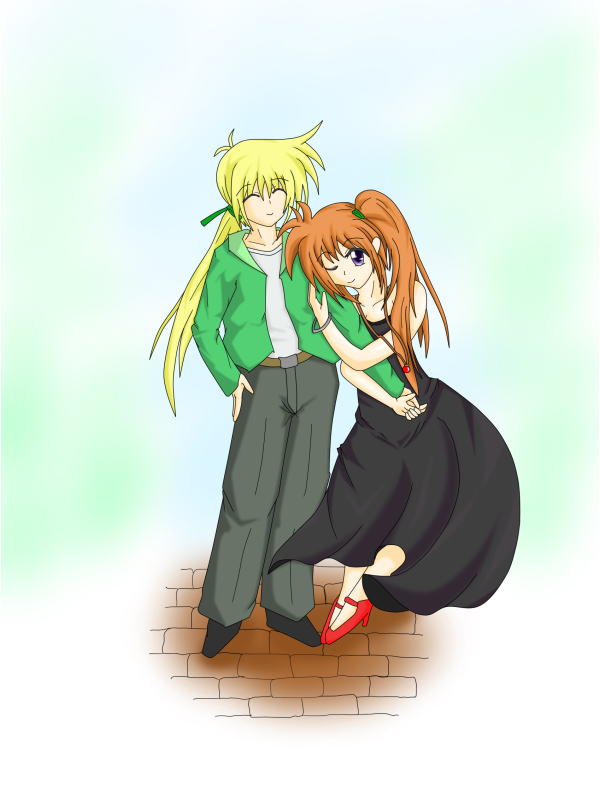
「そんなことないよ。僕だってすごく楽しみにしてたんだから」
「むぅ〜 信じられないなぁ」
たいそう不満そうな顔をユーノ君に向けてやる。
中々会うことの出来ないユーノ君へのささやかなイジワルだ。
そんな私にユーノ君はにっこりと微笑んだ。
「どうしたら信じてくれるの?」
ユーノ君が困った顔をしてこちらを覗き込んでくる。
私は、数秒う〜んと考えると、いい考えが思いつき蠱惑的な笑みを浮かべた。
「…………ここで、キスをしたら許してあげる……」
別に本当にキスをしたかったわけではない、ただユーノ君の困った顔をもっと見たかっただけだ。
だってここはミッドでも有名な場所だ。しかも今日は休日のお昼過ぎ。街行く人は、いつもより多い。
――こんな人前でキスなんてされたら、恥ずかしくて死んでしまう。
「――それじゃあ、お言葉に甘えて……」
「……えっ……つて、んぁ……んんっ……」
気付いたときにはもう遅かった。私の唇はユーノ君の唇でふさがれていた。
――ユーノ君の熱いキス。
こんな人前で。みんな見ているのに。
そう思ったとたん、頭からボンッと何かが爆発するような音が聞こえたような気がした。
同時に、プシューと白い煙も出てきたようだ。
言うまでもなく、私の顔は熟したリンゴよりも紅く染まっているだろう。
「……ゆ、ゆゆ、ユーノ君!?」
慌てて言い返す。
身体が熱く火照っている。心臓がドキドキと鼓動を鳴らしている。
「どうしたの? 僕はなのはの言ったとおりにキスをしただけだよ?」
首を傾げながら、ユーノ君が聞いてくる。
その言葉を聞いて、さらに顔が赤くなったのを感じる。
「……だ、だからって……こんな人前で……」
何とか言えた言葉がそれだった。
頭の中がボーとして、フワフワした気分になってくる。
そんな私を見たユーノ君が、私を抱きしめて尋ねた。
「――嫌だった?」
「………………嫌じゃない……」
私は真っ赤になりながら、その一言だけははっきりと言った。
まずはミッドチルダの街に出かけた。
ユーノ君の手を引っ張って大通りまで移動する。
ちょっとした手と手の触れ合いでも、すごく幸せな気分になってしまう。
大通りには人が溢れ返っていた。
ユーノ君の手を、ギュッと握り締める。
――離れないように、離さないように。
「――さぁっ、ユーノ君。最初はどこに行こうか?」
そして私達は、街に繰り出した。
――楽しい時間というものは、あっという間に過ぎてしまうもので、それは私にとっても同じだ。
いつの間にか暗くなり、街灯が辺りを明るく照らしている。
私達がいる場所も、最初にいた公園だ。
もう楽しい時間も終わり、漠然とそう思ってしまう。
「……ユーノ君、明日の仕事は?」
「いつも通り……朝から夜まで無限書庫に缶詰だよ」
ユーノ君が私を見て苦笑している。
「…………そっか……」
予想していた答えだったけれど、やっぱり落ち込んでしまう。
彼が忙しいのは当たり前なのだ。
「……ごめんね、なのは……」
人気がなくなった公園に、ただただ噴水の流れる音が響いている。
私達もそこでただただ寄り添い合うだけ。
「……今日だけは、私を離さないでね……」
明日が来ればユーノ君は居なくなる。
――だから、今だけは、離れないように、離さないように。
これは私の本心だ。いつもは誰にも見せない心の弱い部分だ。
ユーノ君だけにしか言えない弱音。
ユーノ君だけに聞いて欲しい弱音。
「当たり前じゃないか……僕は君を離さない」
――ユーノ君を抱きしめる。そして彼の温もりを確かめる。
ユーノ君と一緒だからここまでくることが出来た。
ユーノ君と会えたから、ここに居ることが出来る。
そんな事を本人に言えば笑って、『なのはが努力したからだよ、僕は何にもしていない』というだろう。
だけど、やっぱりそれは違うのだ。
ユーノ君と出会わなければ、フェイトちゃんにはやてちゃん、それに守護騎士のみんな、新たに加わった新人達にも会うことは出来なかった。大切な絆をつなげることが出来なかった。
なにより、大好きな……愛している人に会えなかった。
そんなことを想ったら、いつの間にか目には涙が溢れていた。
「……わたし、ユーノ君を絶対に離したくないっ……」
――これは私の我侭。
――これは私の本心。
「――それに、なのは……君にこれを」
ユーノ君が私に何かを差し出す。
小さな小箱だった。装飾も特にないただの小箱。
なんだろうと思いつつ、その小箱をゆっくりと開けた。
「―――ゆ……びわ……」
小箱の中には指輪があった。
真ん中にはダイヤモンドがはめられた銀色のリング。
まさしく指輪だった。
「…………ずっと一緒に居よう、なのは……。僕たちの仕事が落ち着いたら……あ〜、その……」
ユーノ君がポリポリと頬をかいている。その顔は真っ赤になっている。
私は言葉も出せずに、次の言葉を待った。
そして、ユーノ君が何かを決心したように私の瞳を覗き込んだ。
「…………結婚しよう、なのは」
私は気が何処かへ行ってしまったような感覚に襲われた。
――ユーノ君からのプロポーズ。
私が夢見ていた言葉。
どこか心の片隅で望んでいた言葉。
考える必要なんてない。――私の答えなんか決まっている。
「……うん……うん、うん!」
目から涙が溢れてくる。
嬉しすぎて、幸せすぎて倒れてしまいそうだ。
優しく私の手がユーノ君に握られる。
そして、私の指にそっと指輪をはめてくれた。
――その行為は永遠を誓う約束。ずっと一緒に居ると誓うための行為。
そして私達はキスをした。
私達はずっと一緒だ。
明日になってしまったら離れ離れになってしまうけれど、心はいつまでも一緒にある。
――私はきっと離れない。――――離さない。
END
あとがき
当初考えていたものとは違った内容になってしまいました……そろそろ甘々なユーなのSSは控えようかな、と最近考えていますww
SSのページに戻る トップページに戻る